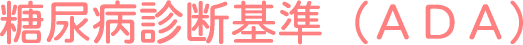
尰嵼丄摐擜昦偺恌抐偵偼倂俫俷丄擔杮摐擜昦妛夛丄暷崙摐擜昦妛夛乮ADA乯側偳偺恌抐婎弨偑巊傢傟偰偄傑偡偑丄嵟嬤偺摐擜昦偺惉場偵娭偡傞婎慴揑丒椪彴揑側尋媶偵傛傝丄偄偔偮偐偺揰偱栤戣偑偁傞偙偲偑巜揈偝傟偰偄傑偡丅崱夞偙傟傜偺栤戣揰傪夝寛偡傋偔丄侾俋俋俈擭俇寧偵暷崙摐擜昦妛夛偼怴偟偄恌抐婎弨傪敪昞偟傑偟偨丅偙偙偱偼偦偺婎弨傪庢傝忋偘偰傒傑偡丅
仭怴偟偄摐擜昦暘椶乮昞侾乯丗崱夞偺俙俢俙偵傛傞怴偟偄摐擜昦偺暘椶偱偼丄兝嵶朎偺攋夡偵傛傝僀儞僗儕儞偺愨懳揑側晄懌傪偒偨偟偰敪徢偡傞摐擜昦傪侾宆偲屇傃丄僀儞僗儕儞掞峈惈偺憹戝偲僀儞僗儕儞暘斿偺晄懌偵傛傝僀儞僗儕儞偺嶌梡晄懌傪偒偨偟偰婲偙傞摐擜昦傪俀宆乮偄偢傟傕儘乕儅帤悢帤偼巊傢側偄乯偲偟傑偟偨丅偝傜偵偦偺懠偺尨場偵傛傞傕偺偺懠偵丄戀帣傊偺塭嬁傪峫椂偟擠怭摐擜昦傪撈棫偝偣傑偟偨丅
昞侾丗摐擜昦偺怴暘椶乮俙俢俙丄侾俋俋俈乯
| 嘥丏 |
侾宆摐擜昦丗兝嵶朎攋夡偵傛傝僀儞僗儕儞偺愨懳揑晄懌傪棃偨偟敪徢偡傞摐擜昦丂 |
|
|
俙丏柶塽妛揑夁掱偵傛傞 |
|
|
俛丏摿敪惈丗帺屓柶塽妛揑婡彉側偳偺徹柧偝傟偰偄側偄応崌 |
| 嘦丏 |
俀宆摐擜昦丗 |
| 嘨丏 |
偦偺懠偺昦婥 |
|
|
俙丏兝嵶朎偺堚揱揑堎忢 |
|
|
俛丏僀儞僗儕儞嶌梡偺応偺堚揱揑堎忢 |
|
|
俠丏鋁奜暘斿慻怐偺昦曄偵傛傞傕偺 |
|
|
俢丏撪暘斿幘姵偵傛傞傕偺 |
|
|
俤丏栻嵻媦傃壔妛暔幙偵傛傞傕偺 |
|
|
俥丏乮僂僀儖僗乯姶愼偵傛傞傕偺 |
|
|
俧丏傑傟側柶塽妛揑婡彉偵傛傞傕偺 |
|
|
俫丏懠偺堚揱惈徢岓孮偵敽偆傕偺 |
| 嘩丏 |
擠怭摐擜昦 |
|
仭怴偟偄恌抐婎弨乮昞俀乯丗崱夞偺俙俢俙埬偱偼丄倂俫俷埬偲斾妑偟偰丄嬻暊帪寣摐偲俈俆倗俷俧俿俿偺俀帪娫抣傪慡偔撈棫偝偣偰掕媊偟偰偄傞偙偲偑拲栚偝傟傑偡丅丅
丂
昞俀丗怴偟偄摐擜昦恌抐婎弨乮俙俢俙丄侾俋俋俈乯
| 侾丗懡擜丄懡堸丄懱廳尭彮側偳偺摐擜昦徢忬偐偮悘帪寣摐抣亞俀侽侽倣倗/倓倢 |
| 俀丗嬻暊帪寣燋寣摐抣乮俥俹俧乯亞侾俀俇倣倗乛倓倢乮愨怘帪娫偼嵟掅俉帪娫乯 |
| 俁丗俈俆倗俷俧俿俿偺俀帪娫寣燋寣摐抣亞俀侽侽倣倗乛倓倢 |
| 仸忋婰俁崁栚偺偄偢傟偐傪枮偨偟丄偐偮梻擔埲崀偺嵞専嵏偱丄忋婰偺忦審傪枮偨偣偽摐擜昦偲妋掕恌抐偱偒傞丅 |
|
| 懴摐擻堎忢 |
俬俧俿亖impaired glucose tolerance丗俈俆倗俷俧俿俿偱丄俀侽侽倣倗乛倓倢亜俀帪娫抣亞侾係侽倣倗乛倓倢 |
|
俬俥俧亖impaired fasting glucose丗侾俀俇倣倗乛倓倢亜俥俹俧亞侾侾侽倣倗乛倓倢 |
| 寣摐挷愡惓忢孮 |
俶俧俿亖normal glucose tolerance丗俈俆倗俷俧俿俿偱丄俀帪娫寣燋寣摐抣亙侾係侽倣倗乛倓倢 |
|
俶俥俧亖normal fasting glucose丗俥俹俧亙侾侾侽倣倗乛倓倢 |
|